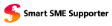この記事の目的
今やビジネスにおいてコンピュータ・情報・通信などを中心とする「IT用語」に対する知識は欠かせません。
あまり馴染みがない各分野のIT用語を、なるべく専門用語を使わずに解説していきます。
この記事の対象読者
Web制作を始めたばかりの人。
自社のWebマーケティングを任された人。
専門用語についていろいろ知りたい人。
Webマーケティングを行なっているが、言葉の定義を再確認したい人。
など、Webに限らずDXに携わるすべての方に。
SEO(検索エンジン最適化)の世界では、ウェブサイトのランキングを向上させるための2つの主要なアプローチとして「ブラックハットSEO」と「ホワイトハットSEO」に大別されます。自身のWebサイトが意図せず検索エンジンからペナルティを受けてしまうことが無いよう、本記事ではそれらの概要と手法について解説します。
ブラックハットSEOとは?
「ブラックハットSEO」は、検索エンジンのアルゴリズムを悪用する技術を指します。具体的には、キーワードの詰め込み、不適切なリンクの作成、そしてコンテンツの複製などがあります。これらの手法は、一時的にはウェブサイトのランキングを向上させるかもしれませんが、ユーザーの利便性を著しく損なうため、ペナルティの対象となる可能性があります。
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって価値ある情報を提供するために、様々なアルゴリズムを使用してウェブページの順位を決定しています。ブラックハットSEOは、これらのアルゴリズムの弱点を突くようなスパム的な方法で検索順位を操作します。
2000年代にブラックハットSEOが横行した結果、質の低いページが検索結果の上位に表示されることが増え、利便性が著しく低下しました。。Googleはこれに対処するために、2011年に大規模なアップデートを行い、ブラックハットSEOの手法を使用したページにペナルティを課すようになりました。
Googleのアルゴリズムについは別のページで解説しています。

ホワイトハットSEOとは
一方、ホワイトハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに従いながら、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供するためのSEO手法です。ホワイトハットSEOは、ウェブサイトの使いやすさ、情報の精度、コンテンツの質などを重視し、ユーザーの検索意図に基づいて最適化されたコンテンツを提供します。これにより、検索エンジンがウェブサイトを自然に高く評価することが期待されます。
以下のページではホワイトハットSEO(コンテンツSEO)について解説しています。

ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いを理解することは、ウェブサイトのSEO戦略において、非常に重要です。ブラックハットSEOの手法は一時的な成功をもたらすかもしれませんが、それは短期的なものであり、ペナルティのリスクを伴います。一方、ホワイトハットSEOは時間と労力を必要としますが、長期的な成功をもたらします。
ブラックハットSEOの手法一覧
隠しリンク、隠しテキスト
隠しリンクや隠しテキストは、ユーザーが見ることができない位置にリンクやキーワードを配置する手法です。コンテンツを不自然にすることなくキーワードを大量に含めることを目的としています。背景色と同じ色のテキストを配置する、要素を非表示にするなどして、ユーザーには見えず、検索エンジンだけがそれを認識します。
今では偽装行為としてGoogleのガイドラインへの違反に該当します。
自動生成されたコンテンツ、大量生成されたコンテンツ
自動生成されたコンテンツとは、プログラムを使用して自動的に生成されたページです。こういったコンテンツは離滅裂なテキストであったり、キーワードを不自然に詰め込んだ文章であったり、または他のサイトから無断で複製したテキストを含むことがあります。これらは、ページの量を増やすこととキーワードの含有数を上げることを目的としています。現在ではユーザーの利便性を損なう行為としてGoogleのガイドラインへの違反にあたる可能性があります。
被リンクの大量設置
ブラックハットSEOの一つの手法として、意図的に他のサイトからの被リンクを大量に増やすことがあります。この手法は、検索エンジンが「多くの被リンク=人気のあるページ」と判断することを悪用しています。リンクの売買、過度な相互リンク、コメントスパムなどの方法が利用されることがあります。
ブラックハットSEOとみなされる被リンク
- リンクの売買: リンクを直接購入するか、他のウェブサイトにお金を支払ってリンクを設置させます。これは検索エンジンのガイドラインに違反する行為です。
- 過度の相互リンク: 無関係なサイトと大量の相互リンクを作ることで、被リンクを増やします。これは自然でないリンクの形成とみなされ、ペナルティを受ける可能性があります。
- コメントスパム: ブログやフォーラムに自動化されたプログラムを使用して大量のコメントを投稿し、コメント内に自サイトへのリンクを含めます。これもスパム行為とみなされます。
これらの手法はランキング操作を目的としたリンクとみなされてGoogleのガイドラインに違反に該当する可能性があります。
ブラックハットSEOとみなされた場合のリスク
ブラックハットSEOの手法を使用すると、検索エンジンからペナルティを受けるリスクが高まります。ペナルティは、検索順位の低下や、最悪の場合はインデックスからの除外という結果もありえます。
ホワイトハットSEOの手法
高品質なコンテンツの提供
ホワイトハットSEOでは、ユーザーにとって有益な情報を提供する高品質なコンテンツを作成します。これは、検索エンジンがユーザー体験を重視しているため、有益なコンテンツは自然と高い評価を受けます。
どのようなコンテンツが有益と判断されるのかは、以下の記事をご参考ください。

サイト構造の最適化
サイトの構造を整理し、使いやすくすることで、ユーザーの滞在時間を延ばし、ユーザーエクスペリエンスを向上させることで、検索エンジンはサイトを高く評価します。

モバイルフレンドリー
モバイルデバイスでの閲覧が増えているため、ホワイトハットSEOではモバイルフレンドリーなデザインを重視します。
正当な被リンク
ホワイトハットSEOで推奨される手法で被リンクを増加させます。
ホワイトハットSEOによる被リンクの増やし方
- 高品質なコンテンツの作成: 高品質で有益なコンテンツを提供することで、他のウェブサイトが自然にあなたのサイトにリンクを張るようになります。
- ゲスト投稿: 業界関連のブログやウェブサイトにゲストとして記事を投稿し、その中で自サイトへのリンクを含めます。ただし、これは適切な方法で行う必要があります。スパム的なゲスト投稿は避けましょう。
- 協力的な相互リンク: 業界内の他の企業や団体とパートナーシップを結び、お互いのウェブサイトで触れ合うことができる場合、自然な被リンクの形成が可能です。
- ソーシャルメディア活用: ソーシャルメディア上で積極的にコンテンツを共有し、フォロワーとエンゲージメントを増やすことで、間接的に被リンクを増やすことができます。
- プレスリリースとメディア: 新製品やサービスの発表、重要な企業ニュースなどをメディアにリリースすることで、報道機関があなたのウェブサイトにリンクを張る可能性があります。
- インフルエンサーとの協力: 人気のインフルエンサーと協力して、彼らのフォロワーに対してあなたのコンテンツやサービスを紹介してもらい、被リンクを増やすことができます。
- コミュニティへの参加: 業界のフォーラム、Q&Aサイト、ソーシャルグループに参加し、価値ある情報を共有しながら自サイトへのリンクを含める。ただし、これも適度に行い、スパム的な行為は避ける必要があります。
- 資料やツールの提供: 独自のデータ、無料ツール、資料を提供することで、他のウェブサイトがそれらにリンクを張ることがあります。
これらのホワイトハットSEOの手法は、ウェブサイトへのアクセスを増加させ、ウェブサイトの権威の向上に役立ちます。ただし、被リンクを増やすプロセスは時間と努力が必要ですが、長期的な成功のためには重要な要素です。
まとめ
Googleなどの検索エンジンは利用者にとって価値あるコンテンツを提供することを重視しているため、ホワイトハットSEOのアプローチが推奨されます。ブラックハットSEOの手法は、短期的な利益をもたらすかもしれませんが、ペナルティのリスクがあり、長期的な成功や信頼性の確立には繋がりません。